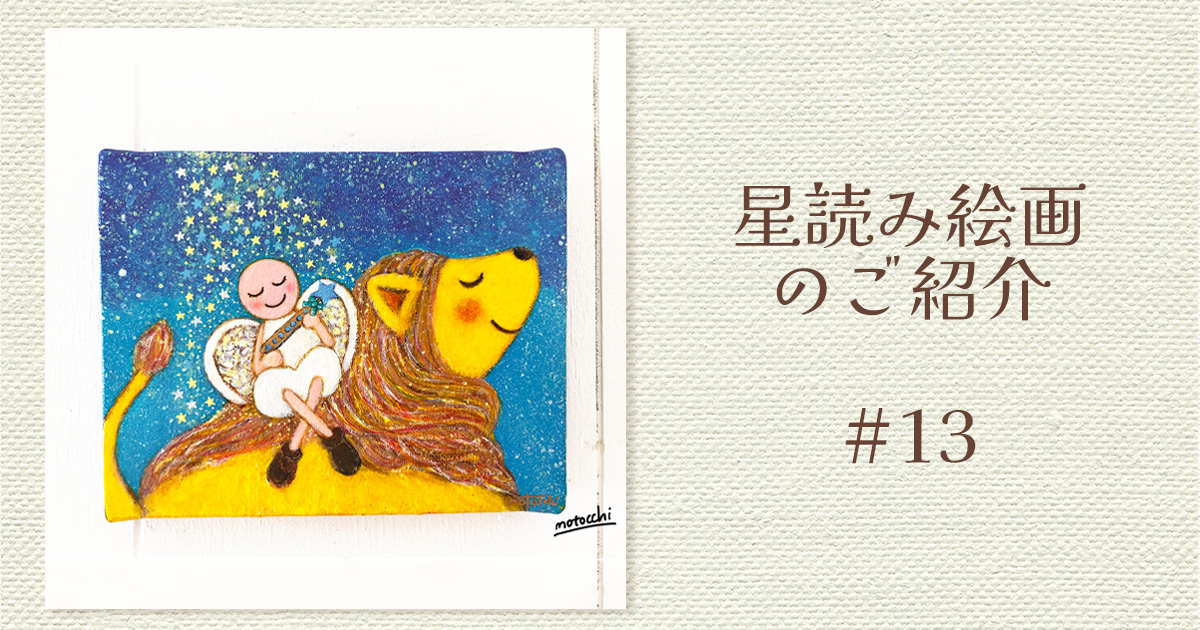「家族」って何だろうって、あらためて考えてみたことって、ありますか?
基本的に、良いものとして語らないといけない空気感ってあると思うんです。
「家族は大事なもの」「家族は温かいもの」「家族は心のふるさと」みたいに。
実際、そういう心の根っこを温めてくれるものであって欲しいと思いますし、そう素直に感じている人も、多いと思います。
でも一枚皮をめくると、家族関係で悩まれてる人も、同時にとても多いと思うんです。
それを表に出して言ってしまうことに、道徳的な抵抗感もあると思うんですけど。
まー、蓋を開けてみれば、当たり前に色々ありますよね。
生活を共にして、人生の時間を重ねるわけですから。
良いことだけではない、悲喜こもごもの濃密な人間ドラマが、そこに繰り広げられているんだと思うんです。
それでこその、赤の他人ではない家族、という関係だと言えるのかもしれません。
ある意味、お互いの「人間修行」の場なんだと思うんです。
個我の目覚め
家族というものを考える時に、一冊の本が思い浮かびます。
何年も前に読んだ本なのですが、ずっと心の中に残っている一冊です。
「他人の始まり 因果の終わり」という本なんですけど、この本はラッパーとして有名なECDさんの自伝的エッセイです。
「家族って何だろう?」というテーマが、彼のリアルな人生体験を通してひも解かれていく、読み応えのある作品になっています。
この本の中で、印象的な描写があります。
ECDさんは1960年生まれなのですが、彼が生まれ育った家庭の中では、「おはよう・おやすみ」と言った挨拶や、「ありがとう・ごめんなさい」と言った言葉を、家族同士で交わすことがなかったそうです。
その理由を、彼はこう分析しています。
家族四人の自他が未分化だったのだ。まるでカエルの卵のように、それぞれがゼリー状の物体に包まれてつながっている。そんなイメージだ。そんな状態から個を確立するには荒療治が必要だった。それが僕の場合は高校を辞めると宣言することだった。
ECD「他人の始まり 因果の終わり」 より引用
今40歳以上の方なら、この感じ、ちょっと分かる部分ありませんか?(それ以下の年代の方は、そういう時代があったんだな、と思ってくださいねー)
挨拶をしない家庭は、さすがに珍しいでしょうけどね。
昭和〜平成初期の親世代の価値観って、今よりずっと集団的だったと思うんです。
個人の幸福より、家の名誉や社会的な立場、世間体に重きが置かれていたと思います。
身内の中でならなおさら、自他の区別があまりついていない。
すごく集団的な自我のあり方だったと思うんです。
「カエルの卵のゼリー」というのは言い得て妙だな、と思います。
私たちはおそらく、歴史の大きな流れで見ても、こうした「集団的な自我」から、「個人的な自我」を確立していく、その流れの中にいるのだと思うんです。
これって実は、魂レベルで大きなチャレンジになっていると、私は感じています。
星読み的に言えば、魂が輪廻転生を繰り返している理由が、ここにあると思えるくらい、人間が一段レベルアップするための、大いなる課題になっていると思います。
これは、それまで包まれていた、ぼんやりとした夢から目覚めていくような体験です。
自分に向き合うことには、苦しみや葛藤がつきまといますし、まー、慣れてないわけですよね、私たちは。
だから「集団に帰属していたい」という意識と、「自分は自分でありたい」という意識が、せめぎ合っているのだと思います。
一歩引いてみれば、こういう段階にみんないて、今まさに試行錯誤している、という理解は必要なんじゃないかな、と思います。
上手く自己表現ができなかったり、集団性と個性のはざまで揺れたりするのは、個我が目覚めていく為に、必要なプロセスなのだと思います。
家族のあり方の変化も、こうした大きな意識の変化の流れの中にあるのだと、思います。
家族のメンバーって実は…
シュタイナー教育で有名な、神智学者のルドルフ・シュタイナーは、「過去世で両親だった人と、人生の半ばで出会う (※1)」と言っています。
これ、ピンとくる人も、いるんじゃないかなーと思うんです。
(「人生の半ば」というのは、30代のイメージですね)
はじめて会ったはずなのに、妙に懐かしさを感じる相手だったり。
このタイミングで出会うべくして出会ったな、と直観的に感じる相手だったり。
特定の相手の顔が、ぱっと思い浮かぶ人も多いんじゃないかなー、と思います。
その逆で、今世であなたが幼年期に出会った両親、兄弟姉妹、幼い頃の友達などは、過去世では、人生の半ばで出会っていた人々なんだそうです。
その過去世でのカルマがあるから、今世で結びつけられるんだそうです。
これが本当だったら、面白くないですか?
今の科学では実証できない内容ですし、あくまで一つの説ですが、家族というものを考える上で、とても示唆に富んだ考え方だと思うんです。
実際に、ご家族全員のホロスコープを並べて読ませていただくと、通常では考えられないような一致点が、現れることがあります。
人智を超えたつながりがそこにはある、としか思えないんです。
偶然、家族になるわけではないし、そのメンバーが集まっている理由がちゃんとあるんです。
作品の制作イメージ

、、と、ここまで「家族」について、あれこれ書いてきたんですが、その理由は、今回ご紹介する作品が「家族」をテーマにしたものだからです。
この絵は、あるご家族全員のホロスコープを読ませていただいて、その上で描かせていただいた「家族の肖像」です。
個性豊かなメンバーを、一枚のキャンバスの上に表現しようとした時、バンドっていうのが一番しっくりくるなー、と感じたんです。
私たちは今、個我の目覚めのタイミングにいる、ということを、先に書かせていただきました。
だからこそ「家族」の形は変わっていくし、個々の個性が発現されていくからこその、苦労があると思います。
でも、それぞれの個性がバラバラに、ただそこにあるわけではなくて、今世で集合していることの大元には、きっと魂レベルでの理由があるんです。
それを良い形で昇華することができたら、それが一番素晴らしいことなんだと思うんです。
その感じを一歩引いた所から見ると、バンドっぽいなーって思うんです。
悲喜こもごもの人間ドラマを繰り返しながら、そこで全員の個性がぶつかり合って、一つのメロディーになる。
どんな時でも、ずっと音楽は鳴り続けている。
そんなイメージで、この作品は描かせていただきました。
ちなみにこの絵は、レコードサイズになってます!(すみずみまで粋でしょ?笑)
この作品をオーダーくださったMさんに、あらためて感謝してます!
Thanks!
(※1)ルドルフ・シュタイナー「人間の四つの気質」(西川隆範訳)を参考にしています。